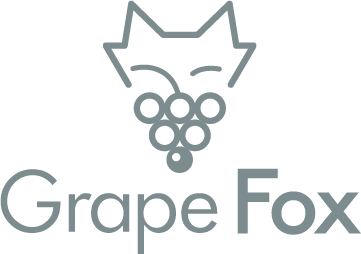Kichi’s Universe吉の物語
01 吉と星降る夜
Chapter 1
キッチンからリビングルームに焦げ臭いにおいと一緒に煙が漂ってきたとき、アニタは肘掛に頭をのせてソファに寝転がっていました。
「フェルナンド!また何か焦げてるわ。」
「何だって?またのろしがあがったって?」
キッチンから元気な声が聞こえてきました。
「もう、違うわよ!パンが焦げてるんでしょ!」
アニタはソファから起き上がって言いました。
「ハハッ!ちょっとふざけただけだよ。はい、はい、私めが片付けさせていただきますとも!」
フェルナンドはふざけて笑いながら、トーストの焦げた部分をバターナイフでこそげ取りました。アニタはいつも通りのフェルナンドに呆れて目を丸くすると、リモコンを取ってテレビをつけました。
「...そして、今週末のメリピージャ区は、最高気温25度、最低気温19度と、かなり過ごしやすい気候になりそうです。残念なことに、にわか雨は期待できないようですね。ここ数年、乾燥した気候が続いています。パブロさんはどう思われますか?」
「確かにその通りですね。メリピラ貯水池の水量はついに半分になってしまい、この地域の農業組合は、国会へ懸念を表明する文書を送りました。議会はようやく高額な海水淡水化施設に税金を投入することを検討し始めましたが、予算についてすでに揉めているようです。」
「なるほど。可及的速やかに何かをしなければならないということは明白ですね。では、今日の天気予報は以上です。ニュースチリをご覧いただきありがとうございました。」
アニタはテレビをつけたときと同じ勢いでテレビを消すと、リモコンを隣のアームチェアに放り投げました。そして顔を手でひと撫でしたあと、髪を後ろでポニーテールにまとめながら言いました。
「今年も雨が降らないなんて......信じられないわ!」
フェルナンドが手には出来立てのオムレツが乗ったフライパンを握ったまま、キッチンから顔をのぞかせました。
「まぁ落ち着きなよ!」
フェルナンドはのんびりとお皿を拭くふきんを肩にかけました。
「そうそう、新しいオムレツのレシピを試してみたんだ。どう?いい匂いだろう!」
「フェルナンド、まじめに聞いてよ!」アニタは少しイライラした様子で言い返しました。
「まあまあ、きっといつかは雨が降るよ。というか、降らないわけないだろ?ぼくらはアタカマ砂漠にいるわけじゃないんだから。」
「そうは言うけど、じゃあ一体いつなのよ?もう7年もまともに雨が降っていないのよ!」
アニタは不満をぶちまけました。世界中で砂漠化が進行していることは間違いありません。実際、「砂漠化」という言葉がトレンド入りするくらいです。
「妹よ、願い事を口にするときは気をつけなくちゃいけないよ。実際に言葉にすると、叶ってしまうこともあるんだから。ハハハッ!」
フェルナンドはいつもの陽気な調子でそう言うと、ダイニングテーブルの椅子を引いて座りました。背中を丸めて両手を合わせ、指を組んだその姿を見て、アニタは、兄が本当は心配しているのだと気が付きました。
「さて、もう一度状況を整理してみよう。ぼくたちの土地には井戸があるよね?」
フェルナンドは声のトーンを少し下げてそう言うと、ブラックコーヒーを飲み干して、渋柿をかじったように顔をしかめました。
「少なくともあと数年は生き延びることができるよ。そう悪いことばかりではないさ。」
「井戸はもう期待できないわ。」とアニタが言いました。
「今朝、技術員と話したのよ。ポンプが水を汲みあげていないの....。」
「まぁ、何とかなるさ。」
フェルナンドはオムレツを食べながらのんびりと答えましたが、その言葉がまったく妹を慰めてはいないことに気付き、アニタの横に座りました。フェルナンドのネクタイには、トーストの破片がついています。
「本当に?」
アニタは皮肉っぽい調子で尋ねました。
「じゃあ、どうしたらいいのか教えてよ...。だって、もうどんな選択肢も残されてはいないじゃない。すぐに雨が降らないなら、私たちはおしまい。以上。」
「別の井戸を掘るってのはどう?それならうまくいくかもしれない。ローンを組んで、プロの水質学者を雇えばいいんじゃないかな。」
フェルナンドが言うと、アニタは顔をしかめました。
「だめかい?別の井戸を掘るっていうのは悪いアイディアじゃないと思うんだけどな。どこかには水があるはずだし...。」
フェルナンドはさらに主張しました。
「雨が降らなければ無理よ、フェルナンド。たとえ水質学者が井戸掘りの名人だろうと、そもそも水がなければお話にならないわ。そう、水そのものがないのよ。地下水は真夏の水たまりよりも干上がっているくらいなんだから。」
フェルナンドは満面の笑みを浮かべました。
「真夏の水たまりよりも干上がっているとは、上手いことを言うね。」
フェルナンドは、最悪の状況でもユーモアのセンスを忘れない妹を尊敬しています。
「何がそんなに面白いのかわからないわ。」
アニタは少し苛立ちながら言いました。そのとき、フェルナンドの携帯電話が鳴り始めました。
「はい、もしもし。はい...あ、はい...わかりました、すぐに向かいます。」
フェルナンドは電話を切るとアニタに向かって言いました。
「ごめん、ICUから呼び出しがかかったから、行かなくちゃいけない。帰ってきたらこの話の続きをしよう。この美味しいオムレツ、食べちゃってくれよ!なんてったってぼくの作るオムレツは、この町一番だからね!」
フェルナンドはブリーフケースを取り上げると、まるで森の中に迷い込んだヘンゼルとグレーテルかのようにパンくずをあちこちに散らばせながら大慌てで出て行きました。
アニタは兄のポジティブさを心底羨ましいと思いました。フェルナンドは人々に愛されるお医者さんです。一方アニタは、体育教師から醸造学者に転身しワイン醸造家になったという異色の経歴の持ち主です。ワイン醸造家はある意味、医師のような仕事でもあります。
アニタは、自分のブドウ畑で育つすべてのブドウの房について、まるで自分の身体の一部のように知っており、細心の注意と愛情を持って手入れをしていました。アニタとフェルナンドは、マリア・ピントという町のブドウ畑を所有していました。その土地に住む知り合いのオランダ人の友人の家を訪ねたとき、その絵に描いたような土地に惚れ込んでしまったのです。オランダ人の友人は天文学者で、空気の澄んだこの地域は研究所を構えるのにぴったりだ、と二人に語りました。アニタとフェルナンドがこの友人の言葉に心から納得したのは、ブドウ園で過ごした最初の夜のことです。ブドウの木をまるで宝石の毛布のように覆う星の光に、二人は圧倒されました。そこで、アニタとフェルナンドは友人への敬意を込めて、自分たちのブドウ園を「スターリー・ナイト」と名づけることにしたのです。
アニタは、収穫から熟成、瓶詰めまで、ワインづくりの全工程に携わっています。フェルナンドは、販売や人事など、主に人と関わる部門を担当し、その人懐っこさを大いに発揮していました。アニタは、兄と自分の性格は全く違うと思っていました。
「私は悲観論者ではないわ。現実主義者なのよ。」
そして今、現実はあまりにも厳しい状況にあります。水不足により、ワインを作るのに長い時間がかかり、コストも高くついてしまうからです。
「これほどひどい干ばつを乗り切れるブドウ畑なんて、世界中どこにもないわ。」
心配で食欲がありませんでしたが、ブドウ園に行く前に何か食べておかないといけません。
「朝食は一日で一番大切な食事なんだよ。その日のエネルギーを生み出すのに必要なブドウ糖のレベルを上げてくれるから。」
いつもフェルナンドがアニタに言い聞かせている言葉を真似すると、アニタはキッチンのテーブルにつきました。ところがフォークを手に取り、オムレツを見たとたん、その顔から表情が消えました。
「乾いちゃってる。」
とアニタはつぶやきました。
「なんてこと、オムレツまでが乾燥しているなんて...。」